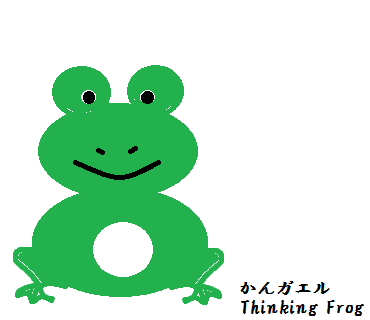木村欣三郎物語 第005話
『農業』
日本からの移民がブラジルに渡り、直面したことのうちの一つ、「農業」について書こうと思う。筆者は、教育に携わっている。子どもたちに、土や植物と触れ合って欲しいという願いを込めて、年間を通じ、色んなものを教室の前の学級園に植えてきた。それは、人間にとって大切なことの一つ「生きる」ことを教えたかったからである。
自分の家から持ってきたトゲのないバラ(トゲがあると児童が怪我したら困るという教育的配慮)、黄色いマーガレット、サツマイモ、ヒマワリ、トウモロコシ、レタス、二十日大根、ニンジン、ピーマン、フェイジョン、たくさん植えた。コーヒーの苗も植えてしまった。叱られるかもしれない。あとで、引っこ抜かれるかも知れない。いつも、有給休暇が終わり、初出勤した日に、悲しい光景を見かけることが多い。だから、ちょっと心配である。これら以外にもアフリカンバイオレットやカランコエの花の苗やパッションフルーツも作った。日本のパッションフルーツなので、花も実も小さいが、とてもきれいな実ができた。
私のことはいいとして、最近の子どもたちは、野菜の名前を知らない、何を食べているのか分からないから始まって、なんの種かも分からない、種を植えたらあっという間に芽が出て大きくなって実ができると思っている子どもが多い。マンガやゲームの悪影響としか思えない。マンガやゲームは、デフォルメして、全てが子どもたちに伝わっていく。しかも、何回か死んだのちにゲームオーバーになる。それに加えて、すべてが疑似体験である。良い面もあるが、悪影響もある。この一年間、子どもたちと一緒に植物を植えていて、そう思った。土をいじれば、汚い。ばい菌が体に入っては大変。土は汚いし、外は治安が危ないし...だから、外の世界を疑似体験して楽しむ、そして、何も知らない子どもたちが誕生し続けている。このようなことがいつまで、続くのだろうか。
『木村 欣三郎と農業』
さて、話は今から、八十年くらいさかのぼってみよう。木村 欣三郎は、兄嫁とブラジルに渡った。そして、農業を始めた。そこで、疑問に思うことは、いくら八十年前の日本とはいえ、木村 欣三郎は、いでん醤油の木村 傳兵衛の従兄弟。彼にとって、農業は、近い存在だったのだろうか。都会育ちでそれほど、農業について、詳しかったとは思えない、という考えでよいのだろうか。ただ、私の祖父母は、家の前を耕して、自分の食べる分の野菜を植えていたのを覚えている。ということは、当時の日本人にとって、農業というものは、日本人の生活に必要不可欠なものだったと思って間違いないと思う。とはいっても、農業を職業として生計を立てるほど木村 欣三郎は、農業をしていたとは思えない。しかも、野菜を植えたところで、南米のブラジルで食べる人を見つける方が難しかったことだろう。
木村 欣三郎は、農家出身の息子ではないから、ブラジルに渡って、大きな農場に寝泊まりをしながらの生活はかなりきつかったに違いない。
『借地』
木村 欣三郎は、兄嫁を兄のところに連れてきたところから、彼のブラジルの歴史は始まる。その兄のところでお世話になり、その後、サンパウロ奥地を転々とする日々を送った。当時の日本からの移民たちは、大農場の一部を借りて農業を営んだ。と書けば、なるほど...と思う人も多い。しかも、借地の契約は、だいたい3年。3年ごとに、大農場を渡り歩く生活がほとんどの日本からの移民の生活。家財道具やお金も少々、持ってきた日本からの移民たち。もちろん、夢や希望も一緒に持ってきた。ところが、彼らのお金というより、小金は、すぐに底をついてしまうことになる。
『大農場での生活』
大農場は、空気がいい。朝、起きたら気持ちがいい。そんな風に思えるのは、観光客だけだ。大農場で働いた人たちに聞けば、きっと、
「何、考えてるんだ」と言うことになるだろう。
日本の昔の話を思い出してほしい。「借地」と書いた。借地をして、儲かった家族もある。儲からなかった家族も当然ある。儲かったら、もちろん、財産も増えるし、楽しい生活を送ることができる。大農場を購入して、大成した人もいたのは、事実である。人生、それほど、楽なことは、夢のまた夢という人がどれだけいたことだろうか。
奈良時代、日本は班田収授法というのがあった。国が子ども一人生まれるごとに、土地を与えるというもの。その代わり、人々は、租という税を国府に納めなければならなかった。収穫の約3%。大したことじゃないかって思う人がいるかも知れない。では、どれほど苦しい生活を奈良時代の日本人はしていたかというと、万葉集にこんなのがある。現代語訳して書くと、
「人並みに耕作しているのに、ボロを肩にかけて、今にも倒れそうな家の中で、地べたにわらを敷いて、両親は私の枕元に、妻子は足元にいて、(今のわたしたちの生活を)悲しんでいる。米を蒸す「こしき」には、クモの巣がかかっていて、米も炊いていない日が続いている。(そんな苦しい生活をしているのに...)ムチを持った里長がやってきて、租税を取り立てようと呼び立てている。これほどまでにこの世に生きるということがどうしようもないと思わないことはない。」
収穫のたった3%の租税。いわゆる年貢。もう、生活もできないくらい追い詰められている状態をうたったのがこの山上憶良の「貧窮問答歌」である。
実は、奈良時代の日本人のような生活を借地生活を余儀なくされた当時のブラジルに渡った日本からの移民たちもしてきたのである。
「ムチを持った里長が...」とあるが、ブラジルも例にもれず、そんな人たちがいた。それが、大農場で雇われていた「カッパンガス」である。簡単にいえば、農場を守る人たち。農場のガードマン。ブラジルの大農場の生活は困窮を極めた人たちも多い。そんな生活を続けるわけにはいけない。農業をあきらめよう。そんな気持ちになったブラジルに渡った日本人たちは、多い。彼らは、勇気を出して、夜逃げをした。「カッパンガス」に見つけられれば、銃殺されてもおかしくない。そんな危険を覚悟して、夜逃げをした。いまでこそ、「夜逃げ」は、死語になりつつある言葉だが、当時は日常茶飯事であった。今は、人に隠れて「夜逃げ」するよりも、白昼に堂々と「逃げる」人たちが多い。
さて、木村 欣三郎はどうだったかというと、兄のシャカラ(とはいえ、大きな土地だが)を後にした。この時、すでに結婚をしていた。木村 欣三郎の妻の名前は久子。久子と欣三郎は、サンパウロの奥地を転々とする生活をしたのである。勇気があったものだと思う。何もないところからの出発を夫婦で始めた。
落花生、綿などを植え、あっちこっちの生活。電気もない生活。水は、井戸。電力がないから、井戸から水を汲む作業があった。大変な毎日の生活をしていたに違いない。日本でも、井戸水の生活をしていた家族は沢山あるから、井戸水を大切に使う精神は、ごく当たり前だったに違いない。
『雨を占う』
当時のブラジルの農業は、雨を頼っていた。電気もないから、灌漑用のポンプなど動かすこともできない。仮に、電気があったとしても、それだけの灌漑施設を購入する資金が不足したに違いない。農家にとって、基本は、土壌分析、播種、施肥、雑草のコントロールなどであるが、まず、いかに天気を正確に当てるかが大切である。とくに長期予報が大切なのだが、当時、そんな情報を手に入れることは、まず、不可能だった。播種時期によって、おおよその収穫時期が決まる。播種するときには、水が必要だし、収穫時期には、雨はいらない。そんな時期を選ばないといけない。ブラジルに渡った日本人たちは、月の満ち欠けを見ながら、その時期を決定した。たとえば、播種は、満月にするといい。定植は、新月にするといい。農業ではないが、正月、5月、9月には、味噌をつかない方がいい。竹を切るなら、6~8月、などなど。いろいろある。
信じるも信じないも、やってみる価値はあると思う。満月には、カニを食べない方がいい(タマゴがないからまずいそうである)。出産は、満月に多い。満月は、狂暴になりやすい。だんだん、農業から離れてしまった。ちょっと、話を戻してみると、農家が蓄えてきた昔からの知識は...
「夕焼けに鎌を研げ」(何事も準備が肝心)
一般的に、天気は西から東に変わる。西の空が明るい夕焼けは、明日は晴れということ。だから、鎌を研いで草刈りや稲刈りの準備をしたほうがいい。
「二百十日は農家の厄日(台風シーズンに注意)」
二百十日は立春から二百十日目のこと。ふつう、平9月1日。閏年だと、8月31日。立春から二百十日は台風が多いから、気をつけないといけない。とはいうものの、気をつけようもない。
「稲光は豊年の兆し」(稲妻は豊作)
雷があると豊作になるらしい。だから、雷光が稲を妊娠させるだろう。そこから、雷光のことを「稲の夫(つま)」。それが、江戸時代に、夫→妻に変化して、「稲妻」。実は、これ、科学的根拠があり、空気の成分の窒素と酸素が雷のエネルギーによって窒素酸化物に変化し、それが雨水によって硝酸になる。それが、農作物にとって、いい天然の肥料となる。でも、自分に落雷したり、農作物に落雷すると、危険。
「日照りに不作はない(日照り=豊作)」
日照りが続く年と、豊作。もちろん、一部に干害の被害はでる可能性はある。
「カッコウのかまびすしく鳴く年は豊年の兆し」
カッコウは夏鳥。5月頃、南の方から日本に渡る。しかも、このカッコウは、他の鳥の巣に卵を産んで育ててもらうずるい鳥。実は、カッコウは、体温保持能力が低くて、天気のいいところに、カッコウは集まる。だから、カッコウの鳴き声がかまびすしく聞こえる年は、天気もいい日が多いし、豊作になるのである。
「寒さが暖かいと凶作」
暖冬だと、凶作になりやすい。暖冬の時は病害虫が死なずに越冬するため、病害虫の被害が増えて凶作になりやすい。そして、暖冬の年は冷夏になりやすく、冷害で凶作になることもある。弱り目に祟り目とは、このことかも。
「厳冬はコメ豊作」
さっきの逆。冬の寒さが厳しければ、夏も天気がよくなって、豊作。冬の寒さで病害虫が死滅するから、、夏の被害も少なくなる。何事も例年並みが一番。
「ダイコンの根が長い年は寒い」
ダイコンは温度に敏感。寒い地域では細長く、暖かいところでは太くなるのが一般的。九州と関東地方の大根の形を比べれば、一目瞭然。そして、寒い年には地下深く根を下ろし、暖かい年には太くなるから、その年の気候を大根の根で判断すればいい。
「ナスの豊作はイネの豊作」
ナスは、暑いと生育が良く、逆に寒いと生育が悪くなる。また、ナスの花が咲く頃に雨が多くなると、花が落ちてしまい、実がつかない。イネもナスも同じ暑い地方のもの。ナスがよく育てば、イネもよく育つ。ナスが豊作になれば、イネも豊作になるってこと。
「夏の東風は凶作」
夏の東風って、オホーツク海の高気圧から吹く風のこと。このオホーツク海の高気圧は冷たい高気圧。ここから吹く風を「やませ」。中学校の地理でもやる知識。その「やませ」が7月から8月にかけ、北日本に東風が吹くと、冷害がおき、凶作になる。宮澤賢治の詩「雨にも負けず」にもでてくる。
「立夏後の雨はムギを害す」
立夏は夏が始まる5月6日頃。日本では、春撒き小麦の成熟期から収穫期に当たる。この時期に雨が多くなると、赤カビ病などの病害が発生しやすくなり、ムギを害すことになる。
いつの間にか、沢山、書いていた。農業に関する言い伝えは、もっと、あると思う。こういった言い伝えを元に昔のブラジルに渡った日本人たちは、農業をしたに違いないのである。そして、勤勉な日本人と言われることから、きっと、現地ブラジルの気候や言い伝えを見逃さなかったわけがない。「言い伝え」や何度かの経験、先に渡った先人達の経験を元に少しずつ、成功の足音を耳を澄ましながら、聞いていたのだろうと思う。
『霜』
この暑いブラジルにも霜が降りることがある。そのとき、天下の分かれ道となる。トマト、コーヒーなど霜に弱い作物は、一気に焼ける。葉が落ちる。実がならない。不作...どころか、凶作。その年の農家の収入はゼロだったらいい。マイナス、つまり、赤字になることがある。農作物に被害を与えるほどの霜は、毎年、降りるわけではない。ただ、降りる年もある。この霜のダメージはとても大きい。ただ、霜の降りるところ、降りないところがはっきり分かれ、自分のところは作物が全滅したものの、隣の土地は、全く霜にやられないということもある。それほど、霜のダメージは、大きい。しかも、霜にやられなければ、どれだけ、儲かるか計り知れない。それが、「霜」である。
『つらい農作業の合間...』
サンパウロの奥地を転々とした木村 欣三郎は、1962年に南マットグロッソにたどりつく。それから、1970年、サンパウロのピエダーデに移るまで、約8年間を南マットグロッソで農業とともに過ごした。木村 欣三郎の家族が大きくなりだしたのは、サンパウロ奥地を転々としているときだ。南マットグロッソでは、木村 欣三郎の孫たちが生まれ、ますます、大家族になっていった。苦しい農作業と子宝にも恵まれた。とはいうものの、病院で子どもを産むわけではない。産婆さんに来てもらって生む。電気もないところだから、医者だって、馬車やトラクタで迎えに行く時代。いまでは、考えられないことだ。だから、木村家の出生率は5割程度。筆者の妻の兄弟は十人。生き残ったのは、5人。残り5人は、死産したり、生まれてすぐに亡くなったり。一喜一憂の生活が続いた。いまでこそ、出産は、それほどリスクが高いものではなくなった。当時は、生きるか死ぬか、手に汗握る瞬間を、夫婦ともに過ごした。夫婦というより、その家族みんながその瞬間を共にした。だから、「出産」に意義があった。いまは、「できちゃった婚」や「おろす」ことを勝手にやって、自由権を乱用しているような気がする。世の中、変わったものである。
話を元に戻そう。だれかが、誕生日だと言えば、飼っていた豚や鶏を殺して、家族のみんなで食べた。あるとき、筆者の妻の父である木村 欣三郎の長男がかわいがっていたヤギが突然いなくなった。当然のごとく、欣三郎の長男がヤギを探した。探しても、探しても見つからない。ふとした時に、見つかった。彼のヤギは屠殺され、お祝の食卓においしそうな肉となり、飾られていた。欣三郎の長男は、悲しがった。いや、というよりも、怒ったと思う。田舎の生活は、家畜を生活の為に飼い、食べ物になる野菜を家の周りに植えていた。ブラジルに渡った日本人は、食材を植えたり、タンポポを食べたり、自然に生えているキノコを採って食べた。木村 欣三郎は、食べられるキノコと食べられないキノコの見分けができた。だから、彼の息子たちがキノコを採って来ると、
「それは、だめ。」とか、
「それは、食べても大丈夫。」と教えていたそうだ。ある物を食べ、ない物は育て、少しでも生活費を倹
約した生活をしていた。ちなみに電気のある生活を始めたのは、ずっとあとのこと。ピエダーデのタカムネさんのところで借地したとき、初めて電気のある生活をする。冷蔵庫も洗濯機もない時代を人生の大半を過ごした。アイロンは、鉄のアイロンを炭で熱くしてから、そのアイロンを振って、火をおこしながら、洋服にアイロンをかけた。お風呂は、ドラム缶である。電気やガスで沸かさない。しかも、お風呂は、家と別なところにあった。暗くなってから、お風呂場まで行かないといけない。この「暗くなってから」が、ちょっと、怖い。お化けがでるくらいなら、まだ、いい。蛇や毒クモと遭遇したときは、ちょっと、大変。雨が降った日も、面倒くさい。電気がないだけで、今の生活とは全く違う生活になってしまう。太陽フレアが活発化すると、停電の恐れがでてくる。そのため、農業に大切な地球の天気予報だけでなく、宇宙の天気予報をだそうと頑張っている人たちもいる。でも、こうやって、電気のない生活をしてきた木村家には、全く問題がないに違いない。むしろ、生活がしやすいかもしれない。先日も泊まったが、サーラの電球が
「パーン」と音を出して焼け、取り換えるのに、大騒動だった。それよりも、ランピオンのゆらゆらと燃える火で、ゆっくりと過ぎてゆく夜を過ごした方が、ずっと、疲れがとれるような気がする。
大家族になった木村 欣三郎は、パラグアイとの境界に近いところで農業を営んだ。そこでは、純粋に農業をするだけでなく、大農場の生活の厳しさも学んだ。
~ その1 BOTECO... ~
農業は、農業ばかりしていたら、倒れてしまう。それほど、きつい仕事である。いろんな人がいたが、畑仕事が終わると、BOTECOに行って、一日の疲れを癒したものである。というわけで、これは、木村 欣三郎の孫のお話である。その孫というのは、筆者の妻。ということは、南マットグロッソでのお話である。その当時、柴田さんとう人がBOTECOを経営していた。筆者の妻、千代子さんを抱いて欣三郎の妻が、その息子である長男(ヤギを屠殺された息子)といつものように、BOTECOに出掛けた。千代子さんは、お腹が空いて泣きやまなかったと言う。
そばにいた黒人の女性がそれを見かねて、ひと言。「わたしが、飲ましてやるから。」と言い、その黒人の乳を飲んで、泣きやんだとか。真相は、よくわからない。その黒人のおばさんは、柴田さんのBOTECOに住んでいたらしい。次にでてくるベネジッタさん、それが、この黒人の女性である。
~ その2 ベネジッタ... ~
もう一つ。そのBOTECOのそばに住んいたベネジッタさん。BOTECOの経営者の柴田さんは、いつもこのベネジッタさんのことを言っていたという。「言っていた」と書いたが、悪く言っていたらしい。このベネジッタさんは、子供の世話以外は何にもしなかったという。ただ、ボーっと一日を過ごしていたというのだ。だから、ダメな人と柴田さんは思っていた。ところが、ベネジッタさんの家の中はとても、きれいに整理されていて、柴田さん自身、びっくりしたという。では、柴田さんの家はというと...BOTECOの仕事が忙しく、汚かったという。 (つづく)
ご意見・ご要望は、わたしの意見箱まで