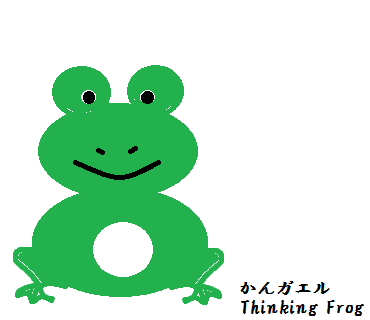木村欣三郎物語 第003話
『カーニバル』
話は前後するが、1930年1月16日(木曜日)に横浜港を出港した。木村欣三郎と彼の夢を乗せたモンテビデオ丸は、3月3日(月曜日)にサントス港に着いた。日本では、ちょうど桃の節句。きっと、暑かったに違いない。桃の節句が暑い時期にあたるブラジル。違和感この上ないだろう。木村欣三郎は、暑さに閉口していたに違いない。木村欣三郎のブラジルに対する第一印象はどうだっただろうか。3月というのに、猛暑である。日本では春一番が吹くような寒い時期。サントス港に降り立った木村欣三郎は希望や夢を持っていたというより、この暑さに閉口していたにちがいない。寒かったところから、47日間をかけ、ゆっくりと時差ボケの影響もなく、ブラジルに到着している。生活リズムが変わって大変だというようなことは、昔はなかった。ただただ、暑い。そして、食べ物。口にあったとは到底、思えない。しょう油屋とはいえ、都会育ちの木村欣三郎。暑い...の一言につきた欣三郎。
ところが、このモンテビデオ丸は、ブラジルのサントス港に到着する前に、リオに寄港している。そして、そこは、カーニバルが真っ最中だった。打楽器中心の旋律。町中がカーニバル一色。とはいえ、現在のような形式ではない。もう少し、小規模に大人しく、そして、お祭りムードに包まれていた。
現在のリオのカーニバルは皆さんもご承知だろう。日本からきた人にとって、カーニバルは、興味深いに決まっている。もちろんのこと、今年も、学校の先生方も参加された。そう、サンバを踊り、しかも、そのチームが優勝。優勝チームの再演にも出場。なんともはや、力の入れ方が昔とちがう。しかも、FaceBookには、ばっちり、本人の写真が承諾も得られず掲載されていた。学校関係者の間では、ちょっと話題になった写真だ。肖像権は?といった問題も、初めて参加して優勝したという気持ちが、肖像権なんてと、うやむやになっていた。海外を飛び回る現代の日本人がこんな感じである。インターネットを介すれば、どこでも誰とでも話すことができる世の中だ。世界の情報を瞬時にキャッチし、そして、送信も気軽にできる時代に生きる人々と好対照な木村欣三郎。LINEやWHATSAPPの存在すら知らなかった、木村欣三郎。もちろん、乗船した船、モンテビデオ丸では、きっと、いろんな説明を受けていたに違いない。カーニバルの予備知識があったとはいえ、実際に見るのとは迫力が違う。当時彼は、二十歳。若い、やせ形の日本男子。言葉が分からなくても、身振り手振りで大丈夫だろう。言葉より伝える能力が大切だからだ。若い彼に伝える能力があったことは、容易に想像できる。日本の雰囲気とは、一風変わった光景に木村欣三郎はどのような感情を持っただろう。驚きともに、打楽器の旋律が体と共振したにちがいなない。日本のお祭を思い出したかもしれない。ブラジル風の太鼓に合わせた歌と盆踊りの決定版、それがきっと、木村欣三郎にとってのカーニバルだっただろう。しかも、音楽をこよなく愛した木村欣三郎である。カーニバルの渦に巻き込まれた、彼の姿を容易に想像できると思う。
日本人にとって、カーニバルといえば、ブラジル風のお祭だ。みんな無邪気にはしゃぐ光景は何ともいえず、初めてみた人でも楽しくなるものである。しかも、日本にも打楽器がある。そう、和太鼓。リズムも旋律も違うものの、打楽器のリズムが鼓動と共振すれば、だれもが何かを感じるはずである。当時のカーニバルは今のそれとは違うが、街中での賑やかさは、日本の祇園祭りを欣三郎は思い出していたに違いない。きっと、楽しく過ごしたことだろう。そして、ちょっとの気のゆるみが、所持金を使い込んでしまったかもしれない。
『新しい生活』
カーニバルの余韻を残し、モンテビデオ丸は、最終目的地であるサントス港にたどりついた。日本の桃の節句。1930年3月3日(木曜日)。この物語と直接、関係はないが、筆者の姪の誕生日でもある。その他、多数誕生されたことだろう。それはさておき、暑い生活の始まりである。彼は、日本に帰ることもなく生涯、ブラジルの地で暮らした。その大地、安全大陸に属する地震のない大地に根を下ろし始めた木村欣三郎。
当時の日本での平均的な生活はというと...。ここに書いてみることにする。東京の朝食はというと、白ご飯、みそ汁、アジの干物、佃煮、漬物である。お昼御飯はどうだろうか。やはり白ご飯、長ネギとわかめのぬた、そして、漬物。夜ご飯はというと、白ご飯にさんまの塩焼き、それに、おひたしと漬物。これが、一日の食事である。もちろん、一例にしかすぎない。ほかにも、納豆、煮豆、塩じゃけ、おから炒り、ぶり大根、シチュー、ほうれん草のごまよごし、お茶漬け(ところによってはぶぶ漬という)。
まだまだ、バリエーションは豊富である。塩昆布、太刀魚の塩焼き、ところによっては、麦飯も食べていた。みそ汁だけでなく吸い物も飲んでいた。これらの食事は都市部の一般的な食卓に並ぶものである。木村欣三郎は都市部に住んでいたから、きっとこんなものを口にしていたに違いない。山間部などでは、夜ご飯が麺類で手打ちうどんを食べる習慣もあった。
みなさんは、ご飯を炊くとき、どれくらいの分量をたくだろうか。一日に一回分を炊くのが普通ではないだろうか。この習慣は江戸時代にできたものである。ただ、東京では、朝に温かいご飯を食べる習慣があったのに対して、大阪では、昼に温かいご飯を食べる習慣があり、翌朝は、固い昨日の残りをお茶漬けにしたり、お粥にして食べていたのである。
ところで、お米は良く研ぎなさいと言われたことはないだろうか。実は、これ、米に付着している糠をとるためである。だから、お米をよく洗いなさいと言われるのは、このためである。そして、そのとぎ汁は、糠が含まれるので、あくぬきに使われた。しつこい汚れをとるのにも使われた。そして、最後は畑や庭の木にまいて肥料となった。循環型社会がここにも見受けられる。循環型社会という言葉は、近年の言葉だが、ずっと以前から実践していたことをただ、もったいぶっていっているだけのような気がするのは、わたしだけだろうか。
ちょっと、この頃の米の炊き方を披露しておく。まず、分量だが、米一升に水一升二合を用意する。ご家庭でやっていることと比べてみると面白いと思う。米は良く研ぎ、火を釜の底全体に火の勢いを強めにしておき、沸騰後に5分後、火から下げ、10分間、蒸らして、櫃にうつして出来上がりである。
白米といっても、大麦や稗、粟などの雑穀を混ぜてたくのも当時としては一般的であった。現在でも五穀米として売られているのは、健康のためだが、この頃生きていた人にとっては、珍しくない商品だということになる。
では、この頃の調理方法はどうだったろうか。まず、旬のものを食卓にだしていた。いまは、四季に関係なく、さまざまな食材が手に入ってしまうから、季節を感じることが難しくなった。どんな風に料理していたかというと季節の野菜、豆、いも、魚介類を生のまま、煮る、焼く、蒸す、茹でると当時も今も同じだった。
当時の日本人が好んで食べたのは、やはり煮物。一度に大量に作ることができるからだ。とくに野菜やイモ類の鍋物。作っておいて何日間も食べ続けていた。調理は水を足して温めるだけと簡単で、時間短縮にもなる。もちろん、だしは、鶏肉や魚介類をつかっていた。
焼く場合は、直火。油は現在のように使っていない。蒸したり、ゆでる方法は現在と変わらない。ただ、この調理は日本独特の方法といってよい。
いままで書いてきてわかったと思うが、サラダを食べていた習慣がない。それよりも漬物を食べていた。みそ汁は食欲を増すし日本の味だから、ブラジルの食卓にのぼっていることが推測できる。しかも、事実である。日本食のベースである煮物。これにはしょう油、砂糖、酒、味噌で調理していた。ブラジルでは、しょう油や味噌は当時、なかった。しかも、野菜がほとんどなかった。野菜を作ったのは、日本からの移民たちだからだ。焼くのには油を使わず直火だから、きっとこの方法で料理していた。ただ、魚が簡単には、手に入らない。奥地に入った日本からの移民は、川魚を釣って食べていたに違いない。蒸したり、茹でたりする料理はしただろうが、手間がかかるので、それほどしたとは思えない。揚げたり炒めたりすることは当時としては珍しかった調理方法である。揚げた場合、煮る工程が入ることが多い。漬物はほとんどが塩漬け。つまり、ブラジルでも容易に実現できたと推測ができるだろう。もちろん、味噌、しょう油、酢、酒粕につければ、レパートリーも広がるが、そんなものが当時のブラジルにはなかった。
では、1930年代の日本の台所はどのようなものだったのだろうか。木村欣三郎が生活していた時代の台所はというと、薪や炭を使っていた。ということはかまどが各家庭にあったということになる。水は、井戸からとるのが一般的であり、水道が使える家庭は少なかった。とくに日本の調理方法では、水を使うことが基本であり、この水を台所まで運ぶことが重労働であった。このスタイルがブラジルにも伝わったのである。
というわけで、当時のブラジルに移住した人たちは、このような生活をしていた。それが、ブラジルに渡り、生活スタイルを変えることができるだろうか。だんだんと変わってくるとは思えるが、なかなか故郷の味を捨てることはできないだろう。新しい味に慣れることも簡単にはできない。筆者自身、ブラジル在住、二十年を過ぎたいまも、ブラジル食に慣れていない。年を経るごとに日本食が恋しくなっている。
木村欣三郎は、都市部に住んでいた。農村部ではない。しょう油屋で育った彼にとって、彼の生活スタイルは、きっと、農村部のそれとは違う。しかしながら、かまどでご飯を炊き、煮物をおかずとして食べ、みそ汁を飲みながら食欲を増し、漬物などの副食が添えられていた食事に慣れ親しんでいたはずである。それが、ブラジルという暑い大地に根をおろし始めた。彼の生活スタイルが変わるとは思えない。ただ、続けるためには、味噌や醤油をなんとかしなければならなかった。
『しょう油屋『いでん』の秘伝 味噌づくり』
ここにしょう油屋『いでん』の秘伝のみそづくりを公開する。読者のみなさんのなかにも味噌を作っている人がいるかも知れない。そんな方にはご参考までに読んでいただければ幸いである。どんなに公開しても、『いでん』秘伝の味噌ができるという保障は全くない。それくらい、味噌づくりは奥が深いのである。木村家でも何人かがいまでも味噌を作っている。筆者の家でも作っているが、それぞれの家でそれぞれの味の味噌ができるのは、とても興味深いことである。筆者が小さいとき、友達の家でよばれたお味噌汁の味は、自分の家のそれとは違っていて、おみそ汁を飲むのが楽しみだった。
それでは、まず、材料から説明する。
- 米 15キロ
- 大豆 20キロ
- 塩 10キロ
- 米麹(味噌麹)の種:各家庭で保管(冷蔵)
- 大きな樽、桶、鍋
- 大豆をつぶす機械
- 作り方
(みそ麹の作り方:『麹に花を咲かせる』という)
お米は、よく洗い一晩つけておく。
1時間くらい、芯がなくなるまで蒸かす。
蒸かした米は、摂氏30度になるまで冷ます。
あまり熱いとみそ麹が死んでしまうので、注意が必要である。
みそ麹の種と蒸かした米を混ぜ合わせる。
発酵し過ぎてしまったら、薄くひろげ、熱をさます。
天候にもよるが、2~3日間で発酵が安定するはずである。
これで、みそ麹が出来上がりである。ここまでの工程でもう3日間が経った。料理には、根気と時間が必要であることは、このことからもわかるだろう。
では、次に大豆の準備に取り掛かろう。大豆は、よく水洗いをして一晩水につける。その後、柔らかくなるまで炊く。大豆を冷まして、できた味噌麹と混ぜ、引き、ペースト状にする。ペースト状になったみそ麹と大豆に塩を混ぜ、桶などの容器に入れ、半年間寝かす。
うまくいけば、半年後、おいしい味噌ができあがる。ただ、大豆を炊くときは、圧力なべを使わないほうがいい。もし、圧力なべを利用したい場合、落としぶたをするといい。それは、炊いている間に大豆の皮がはがれ、圧力なべが大爆発を起こす恐れがあるからである。もう一つの注意だが、大豆の炊き汁は、寝かすまで、捨てずにとっておいた方がいい。それというのも、ペースト状になった大豆とみそ麹があまりにも、パサパサになる場合がある。そんなとき、粘り気をつけるために炊き汁を混ぜるのである。寝かせてからは、1週間に一回の割合で混ぜる。混ぜることによって、発酵を均一にさせるのである。
これが『いでん』秘伝の味噌の作り方である。しょう油屋『いでん』は、つぶれて現存しないが、駅弁などのお弁当の中に入っていたあの小さなしょう油が、じつは、しょう油屋『いでん』の商品であった。木村欣三郎がもし、日本にいたら、ひょっとしたら、現代でも続いていたかも知れないと、いとこの木村傳兵衛は言っていたという。木村欣三郎は、みそを作りはしなかった。ただ、彼の妻や娘にみその作り方を教えただけだった。それが、その孫、千代子にまで続いている。はたして、ひ孫まで続くだろうか。筆者の息子も娘もみそ汁は好きだ。ただ、家族で年に何回か行うみそつくりは、いまだに続いているが、今後のことは全く知る由もない。
いままで、味噌を作ると書いてきたが、本来は、味噌はつくものである。本当は、『味噌をつく』と、書きたかったのだが、どちらがよいかと迷い、最後に書いた方がよいだろうと考え、ここに書くことにした。
みそをつくことの大切さは、日本の心を忘れないようにとしようとしている、筆者の考えからかもしれない。しかし、ブラジルに渡り、この大地に根づき始め、食生活を簡単には変えられなかったからかもしれない。市販の高い味噌を購入したくない。そんな思いもあった。でも、何回か、味噌を作っていく間に『味噌をつく』ことに愛着を覚えるようになった。半年後、忘れたころにおいしいみそ汁を飲むとまた、その味は格別なのである。
みそを作る時期があり、正月、五月、九月は作らない。『正(しょう)五九(ごく)』といわれ、いまでも我が家ではこの月にみそを作ることはない。
『納豆』
材料 大豆 1キロ 市販の納豆 1個
ただ、これは現在の材料である。では、木村欣三郎の材料はというと...
材料 大豆 1キロ トウモロコシの皮 わら
大豆を良く洗い、一晩つける。ここまで、味噌づくりと同じである。そして、大豆を柔らかくなるまで炊く。ここも味噌づくりと同じである。注意も味噌づくりと同じである。大豆が柔らかくなったら、熱いうちに市販の納豆をまぜる。ここがミソである。そして、摂氏40度で丸一日保温しておけば、出来上がり。でも、保温するときは、ふたはしない。蒸れると味が落ちてしまうからだ。味噌も納豆も実は、ほとんど同じ工程である。では、何が違うのだろうか。実は、発酵温度である。味噌はみそ麹をつくるとき、低温でひと肌程度の温度を維持しなければならないのに比べ、納豆は、ちょっと熱めの温度で保温しなければならいないのである。その違いができたときの味を変えてしまうのである。木村欣三郎のひ孫の筆者の妻は、いまでも納豆をつくり、家族で食べ、近くの日本食屋にも卸している。結構、人気の商品である。
ただ、木村欣三郎は、わらやトウモロコシの皮に天然についてる納豆菌を頼りにしていたため、できたりできなかったりと不作のときのほうが多かった。ただ、納豆菌は繁殖力がつよく、納豆をつくるところでは、味噌はできないとも言われている。納豆の嗜好性は低いため、好き嫌いが激しいが、私は、大すきである。
『豆腐』
最後は、豆腐である。筆者の大好物である。豆腐があれば、何も要らない。肉豆腐は、わたしにとって、思い出の料理である。大すきだ。木村欣三郎は、豆腐の型を木で作ったほどだ。それも、かなり大きな型だ。それは、いまだに、筆者の妻の実家に現存する。しかし、だれも使っていない。我が家でも豆腐をつくるは、まれになってしまった。仕事が忙しいのもさることながら、豆腐は、力仕事しなければならず、しかも、『おから』という副産物が大量にできてしまう。それが、豆腐づくりの難点なのである。筆者が小さかったとき、いつも豆腐屋の前を通って、学校に行った。その豆腐屋の前には、大きな『おから』の山ができていたのを覚えている。もったいなぁといつも思って、通りがかっていたが、豆腐を作ってみたら、その訳が分かった。我が家では、大量にできた『おから』は、人間に利用したあと、牛にあげることにしている。我が家には、2頭の愛牛がいる。とても、かわいい。しかも、『おから』は、大好物だから、一石二鳥である。では、そろそろ、豆腐の作り方を説明することにする。
材料
- 大豆 適量 我が家では、500グラムくらい
- にがり 我が家では、Sal amargo(下剤)
- 布袋
- ミキサー
- ガーゼなどの薄い布
- 豆腐の型(ざるやチーズの型も代用できる)
我が家では、豆腐づくりをかなり失敗した。木村欣三郎は、豆腐の型をつくるくらいだから、上手だったに違いない。見よう見まねでする筆者とその妻。たくさんの失敗を重ね、現在は、たまに作るくらいである。本当は、頻繁に作って欲しいというより、頻繁につくろうと思う筆者である。
さて、大豆は良く洗い、一晩、つけておく。ここまでは、いままでと同じである。その大豆をミキサーにかけ、大豆のジュースをつくる。ここで、用意しておいた布袋にその大豆ジュースをいれ、しぼる。これがかなりの力仕事である。握力に自信のない人は、ここで諦めるしかない。または、他に方法があれば、教えて欲しい。この工程でカスがあの有名な『おから』。大豆ジュースが『豆乳』。筆者の妻は、このとき、コップ一杯、豆乳をとり、あとでこっそり飲むのが習慣である。さて、豆腐に必要なものは、この『豆乳』。この『豆乳』を火にかけ、ぐらぐらしてきたら、火を止める。そして、にがりをまぜるとすーっと、透明な液体と分かれるので、固形の部分が豆腐になるところである。そして、用意しておいた豆腐の型に、この液体を少しずつ入れ、白く固まった部分を集め、少し重石をして、固まるのを待つ。固まったら、水を入れた器に移し、冷蔵庫などに入れ保存する。豆腐は、良く水に入れて保存するが、これは、にがりをとるための大切な工程であることを忘れてはならない。筆者は、この工程をだいぶ長い間、していない。自家製の豆腐を食べたときに便通がよくなっていたのは、いうまでもない。
にがりを入れ、かき混ぜるときは、十文字にするとよい。ぐるぐるかき混ぜるといつまでたっても、固まらないのであしからず。この『にがり』については、いろいろなもので代用ができる。筆者は、ブラジルのにがりが下剤であり、薬局までよく買いに言っていた。薬局の人たちは、筆者の買う量に目を丸くしていた。なぜ、そんなに下剤をたびたび買うのだろうと。そこで、筆者は、へたくそなポルトガル語でいつも説明をしていた。そこで、下剤のほかに、代用できるものはないかと探したところ、レモンや酢で代用が可能であることが分かった。そして、行動的な筆者は酢で試してみた。ところが...みなさん、酢は使わないほうがいい。台所中、いや、家じゅうが酸っぱいにおいで、大変なことになった。しかも、気分まで悪くなり、挙句の果てに、豆腐が固まらず、やっとで固まった時には、酸っぱい豆腐が出来上がっていた。その豆腐を食べたら、体がぐにゃぐにゃになるのではないかと思うほど、酸っぱかった。経験は貴重だが、こういう経験はできることなら最初で最後にしたいものである。
『第一歩』
木村欣三郎は、単身でブラジルに来るはずではなかった。しかも、もともと、無口だった。こんな正確も手伝って、誰にもブラジルに渡った理由を話していない。とにかく、ブラジルでの生活がはじまった。彼の一番の問題は、食べ物だったと思う。先にも書いたが、気候は、どうすることもできないから、我慢をしたに違いない。しかし、食事は、しょう油屋の知識をもってすれば、大豆はあるのだから、どうにかできると考えたに違いないのである。そこで、彼が挑んだいくつかの日本食に欠かせない、味噌、納豆、豆腐のつくり方について説明をしてきた。彼は、教えることはあっても、作ることはなかった。作ったのは、豆腐の型。この豆腐の型は、現存する。この道具をみたら、彼が器用であることが、一目でわかるくらいの出来栄えである。彼の器用さは、豆腐の型だけではない。大家族が座れる長椅子もつくった。ベッドも作った。家もつくった。土壁で土間、そして、ちょっと広げようといえば、広げた。それくらい器用な木村欣三郎だった。町の生活しか知らなかった木村欣三郎。その彼がブラジルの地で、家具、家、そして、味噌、納豆、豆腐をつくることに挑戦し、これからの長いブラジル生活に備えていたのであった。
ただ、ここでいつも疑問が残る。木村欣三郎は、本当にブラジルに移住しようと思ってきたのだろうか。瀧を連れてくるためにだけ、ブラジルに渡航したという話もある。真相は謎に包まれたまま、他界してしまった。ただ、一つだけ考えられることは、そうそう簡単には帰ることができないところに来てしまったと感じたこと。2万キロの47日間の旅。その旅の中で彼の気持ちは船と共に揺れていたに違いない。もし、帰るつもりだったら、単身で来ていないのではないだろうか。渡伯することを断念していたに違いないのである。だから、木村欣三郎は、片道切符を握りしめていたに違いないのである。(つづく)
ご意見・ご要望は、私の目安箱まで