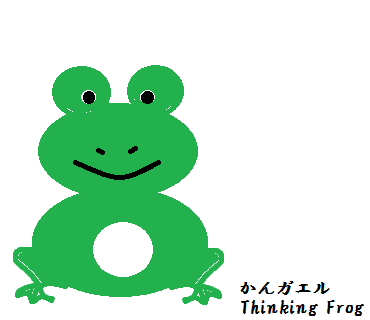木村欣三郎物語 第002話
『ブラジルへの道』
1929年、日本は昭和4年。この前年には第1回普通選挙が行われた。普通選挙といってもまだ、男性にしか選挙権が認められていなかった時代。当時、日本政府の見解は、女性にまで選挙権を与えると社会が変わり過ぎる、世論がまだ、未熟である、女性の政治能力は男性のそれに比べ、稚拙であるなどであった。
そこで、市川房枝らが『婦選なくして真の普選なし』と女性の選挙権獲得を訴え続けていた時代である。この第1回普通選挙では、日本政府の予想を上回る労働者や農民を基盤にする政党からの当選者がでていた。このころ第二次護憲運動が盛んになり、その成り行きとも言える選挙結果だったのである。また、政党内閣が成立して衆議院の二大政党の総裁が交代で内閣を組織する時代を迎えていた。日本全国では日本共産党員の大検挙があった。そして、ソ連では、5カ年計画がはじまり、社会主義の台頭がみられたのである。1929年の10月には、ニューヨークでの株価が大暴落のニュースが世界中を駆け巡った。その2年前、1927年3月には金融恐慌が日本の経済を揺るがしていた。世界的にはアメリカの繁栄、そして、世界恐慌による世界経済の混乱、ロンドン海軍軍縮会議が1930年1月に開催されていた。
こんな時代に日本の移住政策は続いていた。1908年から続いていた移住。ただ、最初の移住では、かなり、お金を持っていなければ、ブラジルに移住することはできなかった。つまり、夢とお金をもってブラジルに渡ったことになる。では、欣三郎はどうだったのだろうか。ひと足先に兄のタカジロウがブラジルに渡っているのである。千代子はシャカラのおじさんといつも言っている、その人である。欣三郎が1930年にブラジルに渡っていることを考えても、それ以前に渡り、それなりに成功を納めていたはずである。なぜなら、弟の欣三郎、正、そして、嫁として瀧(タキ)が呼び寄せられていることからも分かる。
欣三郎は、兄、タカジロウがブラジルに渡るとき、こう言われていたのである。
『欣三郎、ブラジルで待っている』
いや、きっと、こうであったに違いない。というのも、1923年(大正12)、関東大震災があった。そこで、1924年(大正13)2月から、関東大震災の罹災者の南米移住奨励目的で、日本政府は、年齢12歳以上は、1人につき200円(百人分で2万円)の補助を臨時的措置として行った。これが、功を奏して、移住に対する多数の応募者があったのである。けがの功名とは、こういうことを言うのかも知れない。このことから、日本政府は、移民を奨励するためには渡航費の補助をすればいいと、考えるようになったのである。きっと、このことに目をつけて、居づらかった木村家からの脱出をいち早く図り、弟たちを呼び寄せようとタカジロウは考えたのだと思う。長男は家業の醤油屋を継いだ。そして、次男以降は、新天地、ブラジルを目指したのである。小さい頃から、両親を亡くし、叔父、叔母の元で暮らしていた。そこには、愛情こそ存在するだろうが、居づらさの方が大きかったように思う。全てが満たされた世界があるわけではない。第一次世界大戦が終わり、大戦景気も束の間、米騒動、関東大震災、昭和金融恐慌と時代は揺れ動いていた。
ところで、ブラジルでは、1930年(昭和5)、ジェトゥリオ・ヴァルガス(Getúlio Vargas)による革命がおこり、臨時政府は農業移民を除く移民の入国を制限していた。ただ、欣三郎には、都合が良かった。なぜなら、日本移民は農業移民が大半だったので、ブラジルは日本移民を受け入れ続けていたからである。統計データによれば、当時、年に1万2千人から2万7千人が渡航していたといわれている。
そして、その日はついに来たのである。
1929年吉日、欣三郎は新郎の代理として、結婚式に出席していた。ブラジルにひと足早く渡った兄のタカジロウの代わりに新郎として出席するために、茨城県の水海道市にいた。新婦は、瀧(タキ)。旧姓はわからない。しかし、小さいころから、おてんばだったそうだ。髪は短く、頬がでていて、目が大きく、背は比較的、高かった。歩くときは少し前に傾き、猫背だった。その彼女の隣に欣三郎は兄の代役として座って宴のなかにいたのである。これが、日本での最後の宴となった。その後、二度と戻らない日本との送別会にもなっていたのである。欣三郎にとって、一喜一憂だったに違いない。兄のところに行かれる。新天地での生活は大丈夫だろうか。やっと、気苦労の多かった生活から逃れられる。様々な思いが、彼の頭を駆け巡っていた。宴は続いていた。
その数ヶ月前、無邪気な瀧は、彼女の両親から次のように質問されている。
『瀧、ブラジルに行きたいか』
ただ、どこから聞きつけたのかわからない。そして、その質問に瀧は即答した。
『わたし、行く』
もともと、あっけらかんとしていた瀧の性格がそうさせたに違いない。どこにブラジルがあるのか、どんな国なのかも知るよしもない瀧にとって、その答えは何を意味していたのか、わかっていたのだろうか。確かに、当時の日本は、昭和金融恐慌もあり、日本国民は、苦しい生活に喘いでいた時代である。1908年にブラジルへの移民が始まっているが、具体的な情報など、指してなかった時代。そんなとき、即断するのには勇気がいるはずである。実際問題、私自身、ブラジルに移住したという気持ちがいまだにない。もう、20年も日本に帰っていない。それでも、移住しているという気持ちにならないのである。話によれば、欣三郎を呼び寄せた兄、タカジロウの考えは、ブラジルで儲け、日本に帰国することだった。当時の言葉を借りれば、『錦衣帰郷』。そのために弟や自分の嫁を呼び寄せたのである。当のタカジロウは、呼び寄せるまで、どこでどんなことをしていたのか、わからない。彼がいつ、どの船で日本からブラジルに渡り、どの農場に入植したのか、だれも知らないのである。ただ、分かっているのは、マリリアの地でコーヒーを植え、そこそこの人生を歩んでいたことである。だから、弟や嫁を呼び寄せることができたのである。彼の本家は醤油屋。その社長の名前は代々木村傳兵衛。かなり有名な家柄だったようである。従兄の木村傳兵衛(本名:木村伝六)は、水戸市名誉市民であり、1967年11月20日から1972年6月13日までの間、第14代水戸市長を務めた。欣三郎と一緒に育った、木村傳兵衛の訃報を欣三郎が聞いたとき、かなり、落ち込んだそうである。それほど、仲が良かったのである。欣三郎がブラジルに行かなかったら、醤油屋はつぶれてなかったとも言われていた。ただ、欣三郎いわく、
『日本にいたら、戦争で死んでたよ』
こう、いつも言っていたと千代子はいう。一緒に育った傳兵衛も欣三郎のブラジルに行くことに対して、かなり反対していたらしい。たしかに、第二次世界大戦があった。彼がブラジルに来たとき、ちょうど二十歳。もし、日本にいたら、戦争で駆り出されていたはずである。わたしの叔父も戦争で亡くしている。特攻隊で二度と戻らない人となった。ある年の新年会のとき、叔父が悔し涙を流していたのを忘れられない。ただ、欣三郎がブラジルに渡ったのは、1930年3月3日。モンテビデオ丸でサントス港に着いた。1月16日、横浜港を出港した。まだ、寒かったころである。このとき、水戸から出てきて、移住研修センターに滞在していた欣三郎。どんなことを思って、一ヶ月半の大航海に臨んだのだろうか。不安と期待が入り交っていたにちがいない。そして、その60年後、わたしと千代子は、その移住研修センターで出会ったのである。人生とは不思議なものである。
『新天地』
欣三郎と一緒にモンテビデオ丸に乗船したのは、兄嫁の瀧、弟の正のはずだった。ところが、モンテビデオ丸に乗船したのは、欣三郎、ただ一人だけだった。彼の荷物には、バンジョーが一つあった。彼は、バンジョーを弾くのである。ブラジルに着いて、マリリアの地で仕事を始めた。慣れない野良仕事の後、夕日を浴びながら、バンジョーを弾いていたのが、欣三郎。背中を赤く染めながら、弾くバンジョー。欣三郎は、何を思い出しながら、それとも、これからのことを考えながら音を奏でていたのだろうか。
そのバンジョーはいまだにある。大切に千代子の実家に保管されている。1月16日に横浜港を出港した欣三郎を乗せたモンテビデオ丸は、3月3日にサントス港に着いた。
なぜ、兄嫁の瀧や正が欣三郎と一緒に乗船できなかったのかの理由については、調べてみたものの定かではなかった。とにかく2カ月遅れで、ブラジルに到着している。彼らが乗船したのは、さんとす丸。横浜港を5月14日に出港し、6月29日にサントス港に到着している。1カ月半の長旅。その旅は、思い出深いものであった。時計を毎日30分程度、ずらしていた。時化る時もあった。船酔いでご飯を食べられない時もあった。その反面、赤道を通るときには、赤道祭、相撲大会、かくし芸大会、そして、船内小学校や幼稚園が開かれていた。教育熱心な日本人である。乗船していた人々は、さまざまな県からの人だった。しかも、職業も様々だった。学校の先生、商社マン、警官など。このころ、ブラジルに渡るにもお金が必要だったことを先にも書いた。船内で命を落とす人もいた。そんな時のために、祭壇や棺桶も積んでいた。(つづく)
ご意見・ご要望は、私の目安箱まで