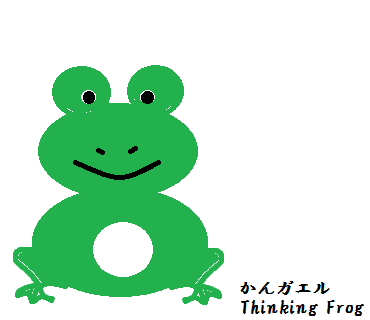木村欣三郎物語 第001話
『素朴な疑問』
千代子は、欣三郎の孫。そして、おしゃべりな小さな女の子だった。髪は短く、ストレート。ごく普通の女の子。ただ、ブラジルの奥地で育った。頭にあることは何でも口に出す。そして、おじいちゃんに、孫の千代子はいつも、頭に疑問があった。そして、こう質問するのである。
『おじいちゃんは、なんで、ブラジルに来たの』
おじいちゃんの答えはいつもきまっている。
『そんなの知らなくていいんだよ、千代タン』
これが、おじいちゃんの口癖だった。
『おじいちゃんは、どんなところで生活してたの』
答えは同じだった。
『そんなの知らなくていいんだよ、千代タン』
千代子はあきらめずに、
『おじいちゃんは、日本でどんな生活をしてたの』
やっぱり、答えは同じ。
『そんなの知らなくていいんだよ、千代タン』
ブラジル日系人三世である千代子はいつも、こう疑問に思っていた。おじいちゃんは、なんでブラジルに来たんだろう。日本って、どんな国だろう。自分のルーツを知ること。それは、大切なことであり、自然なことである。でも、たまに、それを隠す人がいる。それが、意図的なのか否かはわからない。自分のルーツを知りたい。その思いは、自分自身のアイデンティティを見つけたいという気持ちに繋がると思う。自分のルーツを知ることにより、これからの人生が変わるかもしれない。なぜ、日本を離れ、ブラジルを目指したのか。日本を捨てたのだろうか。日本を見捨てたのだろうか。日本を離れた理由を知りたい。まず、そこが知りたいと千代子は思っていた。この物語を書いている筆者自身、日本を離れた。そして、ブラジルに20年以上、住んでいる。いわゆる永住である。でも、自分自身、『永住』というより、『たまたま、機会があったので、ブラジルに住んでいるだけ』といった方が良いかもしれない。昨今は、海外で生活する日本人が多くなった。帰国子女も増えた。家族で赴任するケースがほとんどだからである。企業が国際的になり、現地での円滑な活動のために、そして、現地での自立を目指した人員派遣である。もちろん、日本の本社とのパイプ役にもなる。そんな彼らと筆者は、立場がちがう。まして、欣三郎に至っては、全く違ったものであった。
多くの惨禍を残した第二次世界大戦が終わり、15年の月日が流れていた。日本は、高度経済成長期だった。ベビーブームが到来していた。1960年代のブラジルは、軍政だった。そして、1960年代後半に千代子は生まれた。マットグロッソ(現在は、南マットグロッソ州に属する)の松原植民地のテルセイラリンニャに生まれたのである。欣三郎は、オンゼリンニャというブラジルとパラグアイの国境付近に入植したことがあるらしい。その後、テルセイラリンニャに入植したのだ。そこでは、綿や落花生を植えて生活をしていた。いまでも、欣三郎が綿畑でにっこり笑っている写真が残っている。欣三郎は、日本からブラジルの兄のところ、マリリアにたどりつき、その後、サンパウロ州奥地を転々として、マットグロッソにたどりついた。そこで、孫の千代子は生まれた。このときの生活の様子は後述するとして、千代子の疑問に少しずつ、答えていこうと思う。千代子は、日焼けをした丸い顔で眉毛と目が欣三郎そっくりである。そんな千代子は、小さいころ、ポルトガル語でしか話さなかったという。いまでこそ、日本語教師として、何年も経験を積んでおり、日本語は達者である。でも、漢字はちょっと弱い。今から、20年前に初めて、筆者が彼女に会ったとき、彼女の日本語は、けっこうたどたどしかったのを記憶している。なるほどっと、頷けるところがある。ブラジル奥地で育った千代子。おじさん、おばさんに囲まれ、大家族のなかで育った何事にも活発で積極的な彼女。木造の家に住み、引っ越しといえば、家ごとトレーラーに乗っけられて、トラクタでひっぱったこともあるという。とろとろと田舎道をゆっくり歩くトレーラー。のどかなものである。実際、筆者も結婚後、現地に行ったことがある。そのころものどかだった。千代子と二人で行ったのだが、町から千代子の育ったテルセイラリンニャは、バスで行かないと行かれないほどの距離だった。バスは、そんなに本数があるわけでもない。当時、暑く、バスはもうじき来るころ。まだ時間があると思い、筆者と千代子はアイスクリームを食べながら待つことにした。しばらくすると、バスが近づき、わたしたちの目の前に停車した。ただ、そのバスがテルセイラリンニャまで行くのかわからない。時間も少し早い。きっと、このバスではないだろう、二人はそう思って、アイスクリームを食べ続けていた。そのバスの行き先を確かめなかった二人はあとで後悔することになるとも知らず、アイスクリームを食べ続けていたのである。周りものどかだったが、二人ものどかだった。いや、のんきだったのである。間もなく、バスは、発車した。二人は、どのバスだろうと思いながら、もうじき、来るだろうと思って待っていた。そして、目の前に止まっていたバスがゆっくり走り始め、角を曲がる瞬間、行き先が見えた。テルセイラリンニャ行きのバスだったのである。二人は慌てた。ゆっくり走るバスを全力で追いかけた。アイスクリームを食べている場合ではない。何とか追い付こうと必死だった二人だったが、バスの方が早かった。そして、二人は立ち止まった。二人とも、息が荒かった。アイスクリームを食べるのを忘れ、全速力で走ったからだ。でも...ふと、思った。折角、アイスクリームも食べていることだし、思い切って、テルセイラリンニャまで歩こうと筆者が千代子に提案した。二人は、とぼとぼ歩いて行くことにした。このとき、千代子は、
『テルセイラリンニャは、遠いよ』
と言っていたのを覚えている。
そして、とぼとぼ歩いても歩いても、テルセイラリンニャにたどり着かない。日差しは強く、照り返しもきつい。しかも、町をでると、舗装もしていない道である。車も通らない。全く何もない、道だけがあるそんな田舎道を二人は歩いていた。が、その歩く作業は、そうそう続くわけもなかった。アイスクリームもいつしか、食べ終わり、ただただ、歩いていたが、だんだん、疲れてきた。これを引き返すのも嫌である。折角、何年かぶりにマットグロッソに来たのに千代子が小さいときに住んでいたところを見たいという気持ちが大きかった。でも、歩いても、歩いても、道はまっすぐ。右も左もどこまでも続く草原。のどかなものである。のども渇いてきた。とにかく、暑い。とくに日本で長年過ごしてきた私には、この日差しはきつい。とにかく暑かったのを覚えている。しかも、甘いアイスクリームを食べたので、のどが渇く。ところである。やっと何かが見えてきたのだ。墓地だった。そこには、千代子の弟が埋められているという。休むためにもちょっと、お墓参りをしようということにした。のどをいやす鉄管ビールもあるだろう。うきうきしだした筆者である。ところが、ちょっとした問題があった。千代子の弟の墓が分からないのである。墓地で働いている人をみつけ、日本人の墓がどこにあるか聞いてみることにした。すると、彼は苗字を聞いてきた。
『キムラ...』
彼は墓のあるところを教えてくれた。かくして、千代子と筆者はお参りをすることができたのである。ただ、線香もろうそくもなかった。ただ、手を合わせただけである。わたしにいたっては、義理の弟になるので、まったくわからないが、お参りをした。筆者が日系人の歴史に触れた瞬間でもある。お参りも終わり、二人は疲れ果てていた。もういい、それがお互いの気持ちだった。テルセイラリンニャまで行けなかったけど、弟のお参りはできたから。それが二人の理由だった。来た道を引き返すことにした。二人とも疲れていた。ほんとに『とぼとぼ』が二人を形容するのにふさわしい言葉だった。すると、後ろから、
『バ、バ、バ...』
音が聞こえてきた。タイヤが人の丈もある大きなトラクタが近づいてきたのだ。朗報である。そのトラクタは千代子と筆者をみると、案の定、止まった。別にヒッチハイクの合図をしたわけではない。彼の好意に二人は甘んじた。トラクタって、なんて楽なんだろう。ほんと、そう思った瞬間だった。二人は、ゆっくり風を切って、来た道をもどっている。
『トコトコ...バ、バ、バ、バ、...』
あっとう間だった。トラクタの乗り心地は最高だった。町に着き、お世話になっていた千代子の親戚の家に二人は戻った。
『あら、早かったわね』
あいちゃんが言う。千代子のおばである。ケーキを作っている最中だった。二人とも気まずかった。アイスクリームを食べているうちに、バスに乗り遅れたなんて、言えないからである。しかも、そのバス、二人の前に、だいぶ長い間、停車していたのである。恥ずかしい...。二人は、そう思った。でも、テルセイラリンニャに筆者は行きたかった。千代子がどんなところで育ったのか見たかったからだ。その夜、事の顛末を話した。すると、次の日、おじが車で連れて行ってくれた。F1000だった。乗り心地は最高だった。なんといっても、楽だ。昨日とは雲泥の差だった。炎天下のなかを『とぼとぼ』と歩くこともない。大きな車で『ヒューヒュー』である。とっても、気持ちがいい。ところがである。せっかく、ここまで来たのだから、『お墓参りしていったら...』という千代子のおじの提案が二人を絶句させた。もう、前日、お墓参りしちゃっていたからである。実は、千代子も筆者も『とぼとぼ』歩いていたことを、おじさんにもおばさんにも説明を省いて、伝えていた。しかも、お墓参りしたことなど、一言もいっていない。実は、けっこう町から墓地まで遠かったのである。そこを歩いていたなんて、説明したら、目を丸くするのが目に見えていたからだ。というわけで、2回、つまり2日間続けて、千代子の弟をお参りしたのである。そして、千代子の育ったところにも行くことができた。いまは、もう、千代子が育った家はなかった。そのかわり、大きなマンゴーの木があった。千代子は懐かしそうだった。牧場になっていた千代子の育ったところは、のどかなままであった。そんなところを見て、昔の光景を垣間見ることが筆者はできた。どんなことをして遊んでいたのだろうか。お花を摘んだりしていたのだろうか。家のお手伝いをしていたのだろうか。テレビもなかった。ラジオがあるだけだった。しかも、電池式のラジオである。冷蔵庫もなかった。そんな家に千代子は育った。つまり、電気なしの生活である。いまでこそ、『もったいない』という言葉を全世界に広めたワンガリー・マータイさんの考えが3Rへと発展し、ゴミの減量、再使用、そして再利用という考えが唱えられる前から、千代子の家族は実践していたのである。日系移民の家庭はきっと、こんな感じだったと思う。現在は大量消費時代。そこから、持続可能な社会へと移行しつつある。回帰現象だろうか。筆者は、日常では『社会』を教えている。その中で、いつも、思うことがある。教科書に書いてあることをテストで100点をとることは簡単である。しかし、100点をとった生徒が実践できるかというと、はなはだ疑問である。千代子をはじめ、千代子の家族は人生が節約だった。ご飯を食べられらないほど貧乏をしたわけではない。しかし、もったいないことをすることはなかった。生活の基本が、『もったいない』だった。日本の精神が...というわけではないと思う。自然に『もったいない』だったのだろう。自然に3Rをしていた千代子とその家族。
話が脱線してしまった。話を戻そう。どこまでいっただろうか。
そう、オンゼリンニャについてだった。そこは、国境に近く、治安も悪かったという。そこに住んでいた人ならわかるだろう。しかも、パラグアイから出稼ぎに来ている労働者の不気味さは異様に映っていた。夜、エンシャーダを寡黙に研いでいる姿は不気味である。もちろん、気質が荒いかといえば、そうでもないらしいが仕事に対する執着心は、だれよりも強かったと思われる。
話は変わるが、千代子が日本語に興味を持ち始めたのは、彼女が13歳になったころ。西城秀樹の大ファンになったのである。ポスターを集めていた。いとこも協力して、会館のポスターをやぶり、わざわざ、千代子に郵便で送った。親戚の誰もが知っていた、千代子の西城秀樹へのファンぶり。当時、ラジオで日本語放送を聞くのがやっと。しかも、『シーシー』という雑音とともにかすかに聞こえる日本の曲を胸をときめかせ聞いていたあの頃。今のように、インターネットもないなか、日本の情報は、テレビのローザ三宅の番組かラジオ。
テレビの映像は、サンパウロの奥地に住んでいたため、良いわけがない。磁気の嵐が吹きすさぶなか、目をこらして見ていた。そんな時代だった。
千代子は、西城秀樹の歌詞の内容を知りたかったのである。そのためには、どうしても日本語を覚える必要があったのである。それが、日本語を勉強しようという意欲に火を付けたのである。それが、いつしか、日本に行きたい、という願望に変わり、日本語教師の助手をしながら、日本語を習得していったのである。
ところで、わたしが千代子と会ったのは、1990年のこと。JICAの日本語教師本邦研修1年間コース、通称Bコースというプログラムで来日していた。
わたしは、ブラジルに渡るために研修を受けていた。寝泊まりをしていたのが、移住研修センター。横浜の根岸にあった。そこでお互い、知り合ったのである。
『出会い』は大切である。でも、こんなに大切になるとは、思ってもいなかった。欣三郎の孫とであったのである。そして...
ご意見・ご要望は、私の目安箱まで